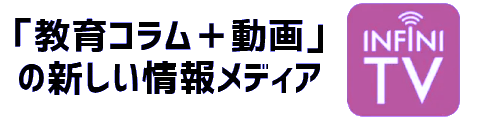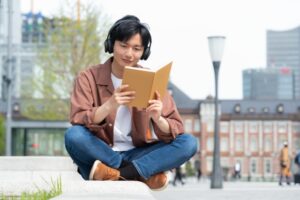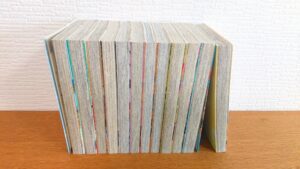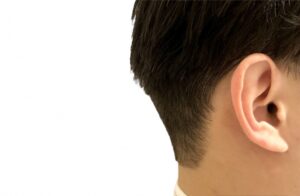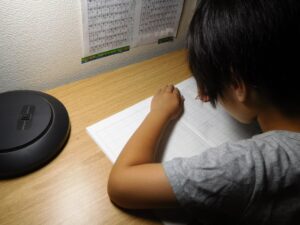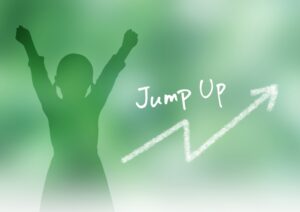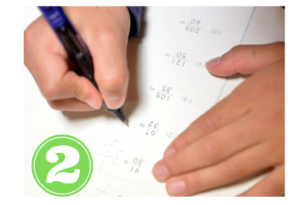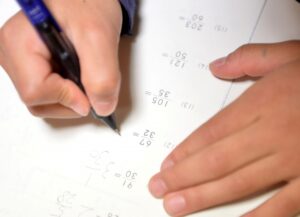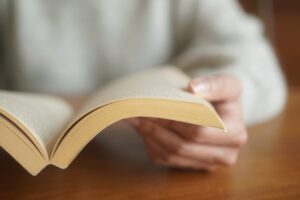InfiniTV03
記憶力が高まる「リトリーバル復習法」とはNew!!
「リトリーバル」(retrieval)とは、一度インプットしたものを脳の中から取り戻すことです。リトリーバルは、100年以上もの研究の積み重ねの中で高い学習効果が確認されてきたインプット法です。リトリーバルを取り込んだ勉 […]
主体的学びービブリオバトルのひと工夫ー
先日、インフィニットマインドの受講生を対象とする『ミニビブリオバトル』を開催しました。ビブリオバトルは、他人にお勧めする本の内容や魅力を紹介し合い、参加者が最も読みたいと思う本「チャンプ本」を決定するプレゼン大会のような […]
「子ども主体の学び」を実現する環境づくり
未来を担う子どもたちが今後も起こるであろう様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことが求められています。こうした背景を踏まえ、学校教育の現場では「子ども主体の学び」が展開されています。 子どもが自 […]
主体性を伸ばす探究学習と非認知能力
学校教育が大きく変化しています。生徒の主体性を伸ばすことを重視した「探究学習」が全国各地で行われています。ここでは自ら設定する課題に主体的に取り組み、仲間と協働で粘り強くやり抜く力が重視されており、いま社会人として求めら […]
良質な集中力トレーニング
<引用・参照>日本経済新聞『今を読み解く』(茂木健一郎)2024.6.8 大人も子どももスマホを持つ時代となり、私たちは「絶え間ない中断」と戦っています。 私たちの仕事中は、様々な通知音によりパソコンの画面から絶えず呼び […]
子どもの視力低下を早期発見
先日、眼鏡市場での待ち時間に小冊子を手に取り、読み進める中で私の過去のかすかな記憶が蘇りました。 私は小学5年生の頃に、黒板の文字がぼんやりとしか見えなくなりました。違和感を覚えながらも、目を細めて見るなどしてしばらくそ […]
自発的に取り組むこと
【引用】2024年6月1日(土)日本経済新聞『データで読む地域再生』 コロナ禍で減ったこどもの運動機会を取り戻す取り組みが全国で広がっています。スポーツ庁が実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査(全国体力テスト)」 […]
大切な「架け橋期」
<引用・参照>令和5年2月27日 中央教育審議会初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会『学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について ~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~』 5歳児 […]
運動は脳の発達を促す
「高齢者の握力が認知機能維持と関連している」という趣旨の記事がインターネット上で公開されていたこともあり、身体機能の維持、認知症予防の目的でウォーキングを日常生活に取り入れる方がさらに増えたのではないでしょうか。 正確に […]
「ニューロダイバーシティ」と「学びの個性」
ニューロダイバーシティ(Neurodiversity、神経多様性)とは、Neuro(脳・神経)とDiversity(多様性)という2つの言葉が組み合わされて生まれた、「脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違 […]
学習を支えるワーキングメモリ
ワーキングメモリは、数学や読解力等の学業成績と関連しています。(Bull & Scerif, 2001; Neveo & Brezniz, 2011など)APA PsycNet 情報を一時的に記憶して処理 […]
変わりゆく「読解力」の定義
OECD(経済協力開発機構)の参加国が共同で開発し実施している、15歳児を対象とする学習到達度調査PISA(ピサ)では、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野を調査しています。 日本国内ではそれらの順位に関し […]
マンガで学ぶ
『AERA with Kids 23秋号(朝日新聞出版)』に「学びにつながるマンガ」という特集があります。 日本のマンガやアニメのクオリティの高さは世界中で知られていますが、それはマンガのタッチだけでなくストーリー性など […]
205.「聞き取り読解テスト」で力をつける
私たちは「受ける度に賢くなる」「受ける度に語彙力・読解力が身につく」をテーマに、新しいテストを開発し、公開しました。一般的にテストは受検時点での力を測るものであり、既習範囲の理解度を測るものです。私たちが開発した「聞き取 […]
204.ことば遊び「比喩バトル」
『実践国語研究2023年10/11月号』(明治図書)に京都大学大学院の三好真史先生による「言葉あそび」が紹介されています。その一つが「比喩バトル」です。 「ジャンケンで勝ったら、物を指さします。負けた人は、その物の色や形 […]
203.言語の習得は「音」から
小学生になるまでは基本的に「読み書き」をしないため、音声により学習をします。耳から聞こえることばを覚え、ことばの数を増やし、会話等を通して使えるようになります。もちろん絵本等を自分で読むこどももいますが、読み聞かせを通し […]
202.書き抜き問題の答え方③
テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]
201.書き抜き問題の答え方②
テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]
200.書き抜き問題の答え方①
テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]
199.学位よりスキル!?
アメリカでは、IBMやウォルマートなどの大企業が人材採用の際に学位よりスキルを求める傾向が強くなっているようです。従来は出身大学等が重視されてきた日本国内の採用においても、今後同じ傾向が出てくるでしょう。但し、学位かスキ […]
198.机に辞書と図鑑を
こどもの学習机に国語辞典や図鑑をさりげなく置いておくことをお勧めします。こどもに何かを身につけさせようという大人の「力み感」を抜くことで、こどもは解放的な気持ちになります。国語辞典や図鑑は、その分厚さが特別な贈り物にも見 […]
197.科学の学びにも「言語能力」
日本政府は科学技術人材の育成に力を入れています。「スーパーサイエンスハイスクール」に指定された高等学校等では、先進的な理数教育が実施され、大学との共同研究や、国際性を育むための取組が推進されています。 スーパーサイエンス […]
196.本をノートにする
わたしの中学校時代のかすかな記憶をたどると、国語の教科書にはたくさんの書き込みをしていました。国語教師の指導によりそのようにしていたのか、自分なりに工夫をしていたのか記憶が定かではありませんが、授業中に教師が教えてくれた […]
195.粘り強さと学力
一般的なイメージとして「粘り強さを持っているこどもは学力が高い」と思う方が多いでしょう。自分のこどもが粘り強さに欠けていると感じると、親としては「HOW」を求め、また粘り強さがスポーツやゲームで発揮されるこどもには、学習 […]
194.五・七・五で表す2023年
本日の読売KoDoMo新聞には時事川柳をテーマにした記事が掲載されていました。世の中で起こった一年、そして自身を振り返るにはとても良いテーマだと思います。 広島で開催されたG7をテーマにした『やっと来た 見て欲しかった […]
193.「記号接地」とワーキングメモリ
読解力や科学など多分野の学力が世界トップ級のフィンランドでは、学力テスト等の結果をもとに原因分析に力を入れています。対して日本は、学力テスト等の結果をもとにその対策に力を入れています。対策とは、点数を上げるために昔ながら […]
192.教科書に書かれていることを正確に読み解く
読解力の向上を重視した授業が全国各地で展開されています。福島県の小学校では、リーディングスキルチェックテストの結果を分析して、授業に役立てています。リーディングスキルチェックテスト(RST)は、国立情報学研究所の新井紀子 […]
191.計算が苦手な理由②
当社のスタッフであり、真栄喜そろばん教室を運営している真栄喜貴弘さんがオンラインセミナー「Edu Semi」で講演した内容や、一般社団法人ワーキングメモリ教育推進協会理事の野瀨さんのnoteの記事をもとに構成をします。 […]
190.こどもの脳から大人の脳へ育つ3ステップ
本来的にこどもの脳は、生まれてから3つのステップを経て、大人の脳へと育っていきます。 ステップ1は、0歳から5歳くらいまでに育つ【からだの脳】です。これは主に間脳・脳幹のことで、呼吸や自律神経、寝る、食べるなど生きるため […]
189.計算が苦手な理由①
本日のテーマ「計算が苦手な理由」は3回にわけて更新します。当社のスタッフであり、真栄喜そろばん教室を運営している真栄喜貴弘さんがオンラインセミナー「Edu Semi」で講演した内容や、一般社団法人ワーキングメモリ教育推進 […]
188.見学から学ぶこと
一般的にこどもの習い事の世界では一定期間の取り組みの成果を「発表会」「大会」「試合」「テスト」といった場で、関わる大人が称える機会があります。そこには当落がある場合もありますが、日ごろの努力を称える機会であるといえます。 […]
187.極端な速読は科学的に不可能
情報が溢れる現代において情報を高速で処理できる能力をつけたいのは誰しもが望むことでしょう。情報化社会を生き抜くこどもたちにも必須の力として、一部の入試問題では超長文化される傾向があります。そこで「速読」が注目を集めて久し […]
186.繰り返し学んで脳に刻む「長期増強(LTP)」
私たちが「学習」という言葉を使う時、それは「お勉強」のことのみならず「経験」や「体験」等の意味が含まれています。私たちひとりひとりの指紋が異なるように、脳も一人ひとり異なり同じものはありません。様々な行動と反応が繰り返さ […]