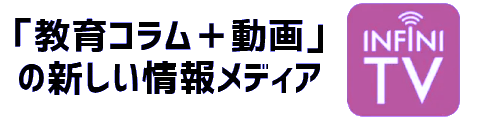96.関連づけできる記憶
『Appleのデジタル教育』(かんき出版)の一節「関連づけできる記憶」には次の記載があります。
2014年、スタンフォード大学医学部で、年齢が異なる子どもの算数問題の解き方に関する調査が実施されました。すると、小学校低学年の解き方は、小学校高学年やティーン(13歳~19歳)、成人の解き方とかなり違うことが明らかになりました。
(中略)
「ネイチャー・ニューロサイエンス」誌に掲載された調査によると、ティーン未満の子どもが問題を解こうとするとき、使用されるのはほぼ脳の【海馬と前頭前皮質】(短期記憶やワーキングメモリを司る)のみで、ティーンや成人になると【新皮質】(長期記憶を司る)と呼ばれる部位に頼るようになります。
つまり、年齢の低い子どもは、頼りにできる長期記憶の数が少ないため、指で数えるなど使えるものは何でも使って問題を解こうとするのです。子どもの年齢が上がって記憶の数が増えるにつれ、検索できる記憶の幅が広がります。人は年を重ねるにつれて、意識的にせよそうでないにせよ、経験を通じて絶えず新しいことを学習しています。そして、経験と経験につながりを見いだす力も向上していきます。
(中略)
脳は絶えず、新たな情報とつなげられる記憶を探し求めているので、探せる記憶の数が増えるほど、新たな問題に関連付けたり、新たなアイデアを理解したりするのが容易になる。私たちはこうした「関連づけできる記憶」を通じてものごとを理解しようとします。
教育関係者にとっての示唆として、生徒に未知の何かを教える最善の方法は、生徒が既に知っていることと関連づけることであり、学習がパーソナライズ化される必要がある、と締めくくられています。
私たちのオンランセミナー等では、長期記憶から情報を引き出して組み合わせるのもワーキングメモリの働きです、と紹介しています。学習のパーソナライズ化という視点においても「ワーキングメモリ」を起点にした学習を私たちは進めてまいります。
#教育コラム96