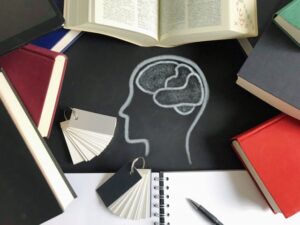266. 「主体的な学び」が学力を引き出す
「家庭の経済と学力には相関がある」というレポートは、新聞やWebメディア等でたびたび報じられています。親の所得や学歴といった「社会経済的背景」(SES)の指標の一つとして、自宅にある本の冊数を挙げ、テスト結果との比較がされています。
2025年度の調査では、算数の平均正答数と自宅にある本の冊数に相関がみられました。本の冊数が少ない児童は正答率が低く、冊数が多い児童は正答率が高いという結果でした。国語、算数・数学、理科の3教科全てにおいてSESが低いほど、正答率やスコアが低くなりました。
しかしながら、SESが低い児童でも「授業では、課題解決に向けて自分で考え、自分から取り組んだ」と回答した児童は正答率が高い傾向にあったことも明らかになりました。家庭の状況にかかわらず、主体的な学びが学力を引き出す可能性があるため、授業を工夫することも大切だ、と締めくくられています。(引用・参照:2025年10月14日(火)読売新聞朝刊「学ぶ育む」)
現行の指導要領下では、主体的な学び、協働的な学びが全国各地で進められています。私たちは、学習指導要領国語科の編纂をされた京都女子大学の水戸部修治先生から全国の学校で取り組まれている事例などを直接伺う機会がありました。「自分が好きなシーンはどこ?」という先生からの問いかけに、目を輝かせてペアワークをする児童の姿に触れ、主体的な学び、協働的な学びの素晴らしさに鳥肌が立ちました。
「主体性」は評価が難しいという問題点も指摘されています。しかし、評価が難しいということが児童の主体的な学びを奪う理由になってはなりません。SESの指標に左右されない平等な学びの場では、主体的学びを育むことに最大限の力を注ぐことが私たち大人に求められています。
#教育コラム266