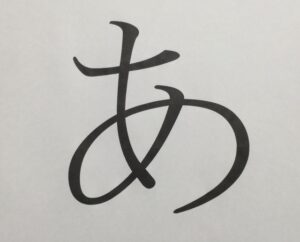270. 社会参加につながる学び
私たちが「語彙」について語る場合、それは主に国語科としての話が多くなりがちですが、広く学習基礎能力としての「語彙」を捉える必要があります。「語彙力」は、学習の基礎・土台であり、それらが多ければ多いほど視野が広がります。
<参照>教育コラム#68.教科書に出てくる「語数」
小学校の教科書に出てくる言葉を「異なり語数」で数えた調査結果が公開されており、それによると国語は2万2,000語、数学は4,200語が登場しています。因みに、「異なり語数」とは、同じ単語を除いた「ことばの種類」のことです。
最も多い語数が登場する教科は社会科で、語数は2万6,000語にも及びます。社会科では地名や人名など名詞が多く登場するため暗記科目として捉えられがちですが、教科名が示す通り「社会」を知り、理解をするために大変重要な教科です。
公職選挙法等の改正により、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができることになったことからも、社会を学び、社会を自分事として捉える重要性が増しているといえます。自分たちの未来は自分たちで考え、行動するという「自立」につながります。
「社会科は暗記科目」といった従来の価値観で捉えることなく、社会参加に欠かせない教養として「社会科」を捉えましょう。子ども達が興味や関心を高めるようなはたらきかけ、環境を用意することが大人にはいままで以上に求められています。社会や政治を身近に感じるような書籍が多く出版されています。お金をかけなくても図書館に行けば無料で手に取ることができます。多くの無料動画も公開されています。
何より大切な働きかけは、大人が「社会」について子どもたちに話しかけることです。テーマはニュースに限りません。社会のルール、経済、環境問題、テクノロジーなど多岐にわたります。「社会」のことばを学び、自分なりの考えを持つことが重要です。
「語彙力」は、語彙の「知識量」と「活用力」の二面で身につけるという教育的な視点を大人が持ち、食事の時間などを活用して話し合う時間を持つことが子ども達の主体的な社会参加を促すきっかけになるのです。
#教育コラム270